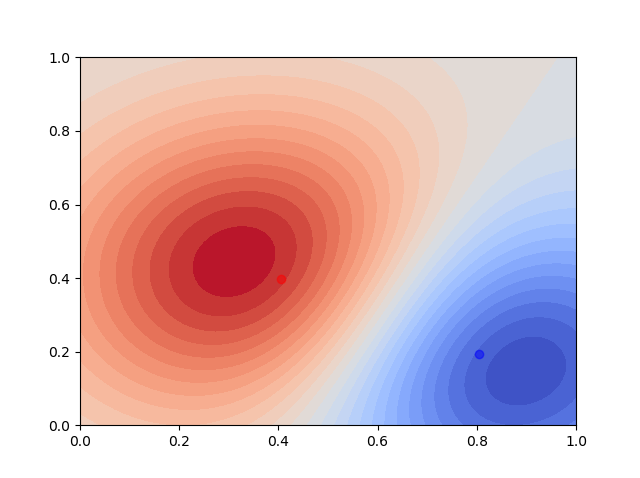ガウス過程による分類(6)の続きです。
ガウス過程による分類(1)~(6)までの長い道のりを経て、ようやく以下の式が得られました。

今回はこれを使って予測分布を求めてみたいと思います。おさらいですが、各文字は以下のようなものでした。
 は各要素が式(2)の行列。
は各要素が式(2)の行列。






式(5)、(6)は、ニュートン法により求める となる点
となる点 を使います。
を使います。
では結果です。
 ガウスカーネルの
ガウスカーネルの を小さくしてみると次のようになりました。
を小さくしてみると次のようになりました。
 結果の図だけ見るとカーネル回帰分析(2)実験結果と似たような感じですね。
結果の図だけ見るとカーネル回帰分析(2)実験結果と似たような感じですね。
訓練データを2点にした結果を見ると、何が行われているのかよくわかります。点を中心としてガウスカーネルが配置されているようなイメージです。中心が少しずれているのは互いの点の影響を受けているためと思います。
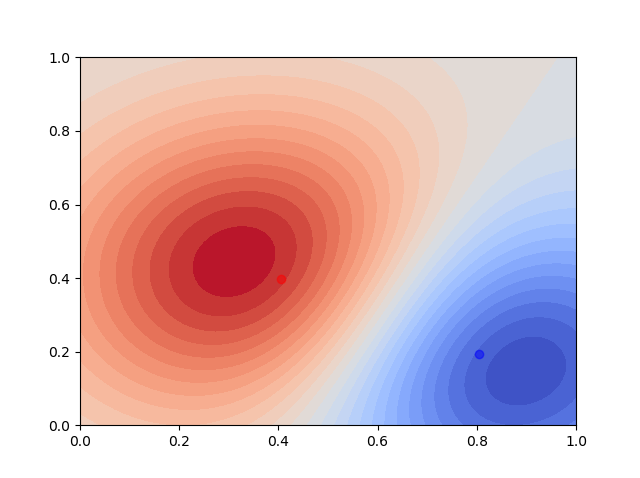
入力を非線形変換したロジスティック回帰でもガウス基底を使って識別をしていましたが、これは基底を自分で適切に設定しなければなりませんでした。一方カーネル法では無限次元の特徴を持つガウスカーネルを使えば、基底をどう設定するか、ということに頭を使わなくてよくなってしまうんですね。
今回のコードです。ニュートン法のイテレーションは適当に10回固定としています。
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
from matplotlib import cm
def create_data(x,y):
if y > -2*x +1 and y > 2*x -1 :
return 1
else:
return 0
def kernel(x0, x1):
sigma = 0.3
return np.exp(- np.linalg.norm(x0-x1) ** 2 / (2 * sigma ** 2))
def gram_matrix(x):
gram = np.empty([N, N])
for i in range(N):
for j in range(N):
gram[i, j] = kernel(x[:,i], x[:,j])
return gram
def sigmoid(a):
return 1/(1+np.exp(-a))
def p_tt(x2, y2):
k = np.zeros(N)
for i in range(N):
k[i] = kernel(x[:, i], np.array([x2, y2]))
mu = k @ (t-sigma_N)
v = kernel(np.array([x2, y2]), np.array([x2, y2])) - k @ np.linalg.inv(np.linalg.inv(WN)+CN) @ k
return sigmoid(mu/np.sqrt(1+(np.pi*v)/8))
np.random.seed(0)
NU = 0.1
N = 100
x = np.random.uniform(0, 1, [2, N])
t = np.empty([N])
t = np.vectorize(create_data)(x[0, :], x[1, :])
a = np.random.uniform(-1,1,N)
CN = gram_matrix(x) + NU * np.eye(N)
for i in range(10):
sigma_N = sigmoid(a)
WN = np.diag(sigmoid(a)*(1 - sigmoid(a)))
a = CN @ np.linalg.inv((np.eye(N) + WN @ CN)) @ (t - sigma_N + WN @ a)
x2, y2 = np.meshgrid(np.linspace(0, 1, 100), np.linspace(0, 1, 100))
result = np.vectorize(p_tt)(x2, y2)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1)
plt.contourf(x2, y2, result,30, cmap=cm.coolwarm)
plt.scatter(x[:,np.where(t==1)][0], x[:,np.where(t==1)][1], color="red", alpha=0.5)
plt.scatter(x[:,np.where(t==0)][0], x[:,np.where(t==0)][1], color="blue", alpha=0.5)
plt.show()